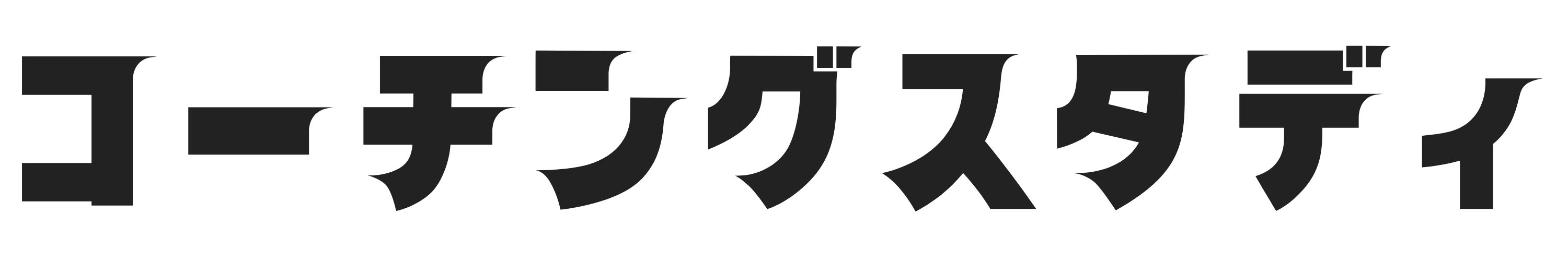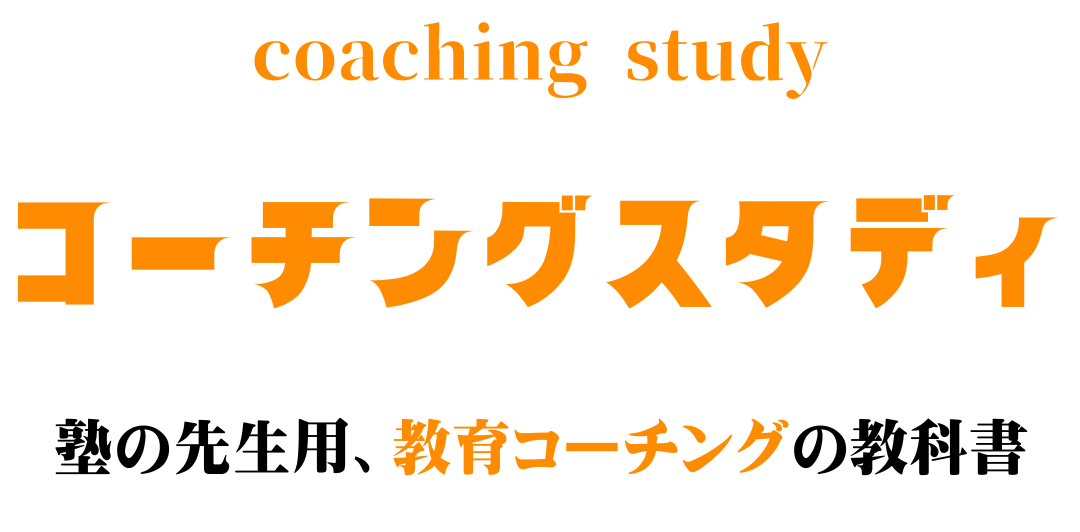コーチングスタディとは?
塾の先生用、
教育コーチングの
教科書
コーチングスタディとは、教育コーチングEdcoacが提供する、
学習塾に向けた小学生から高校生までの
生徒に対するコーチングを学べる動画学習サービスです。
講師全員が、スマートフォンやパソコンでコーチングを
学べる環境を提供いたします。 学生講師研修の一環として導入、
生講師の研修として、新人講師研修の一部としてなど、
活用方法は多岐に渡ります。
現場にいる多くの塾講師の
コーチング力向上に携わっています。

研修動画
- 6分×10本のコーチング研修動画
- コーチング研修動画が何人でも何回でも見放題
- スマホやパソコンでいつでも視聴可能
各動画チェックテスト
- 担当者からのコメント返信
- アウトプットすることで知識が身につく
- 理解できるまで何度もテスト

コーチングスタディには、
“安くて質がいい”以外にも
「選ばれる理由」がたくさんあります。
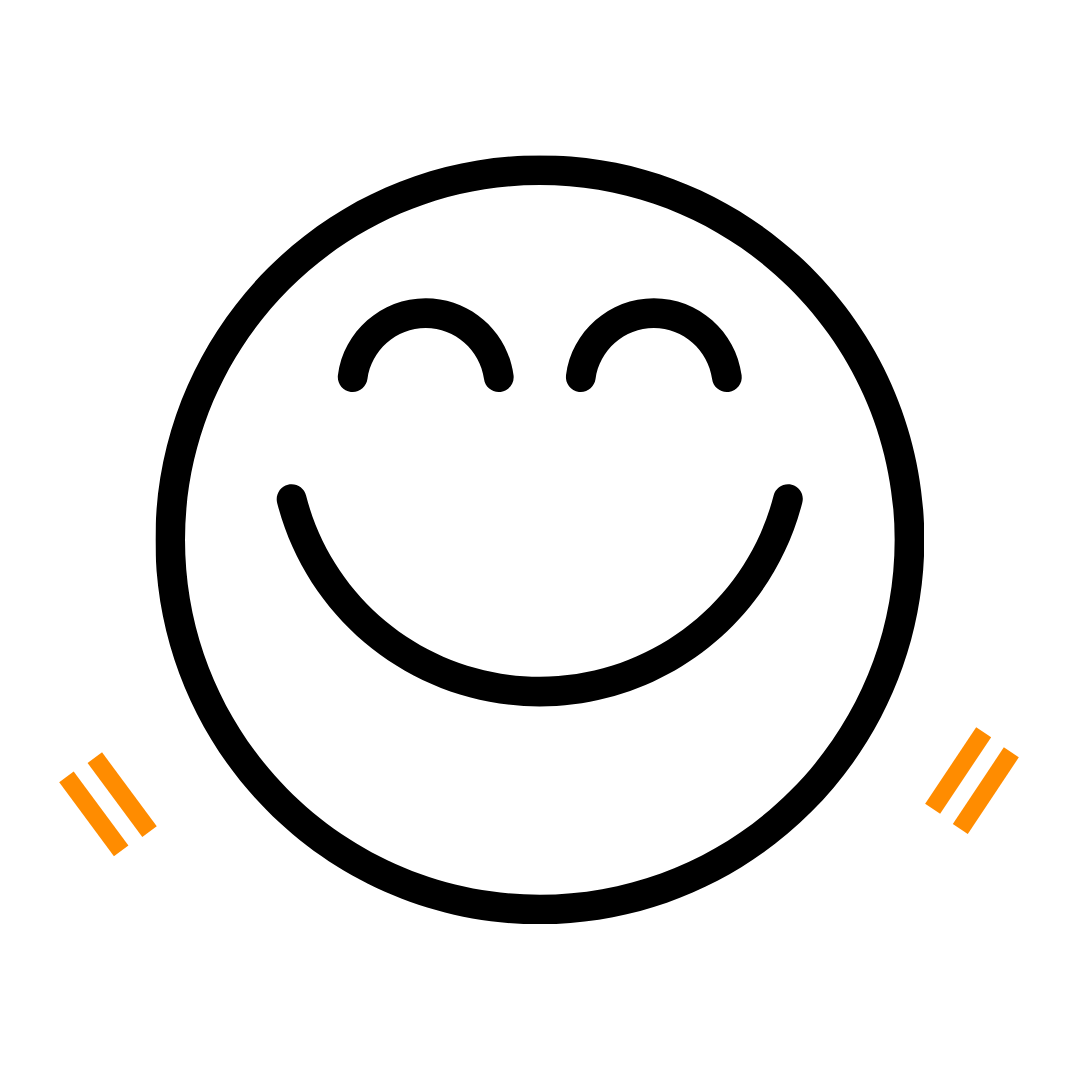
生徒がいきいきする
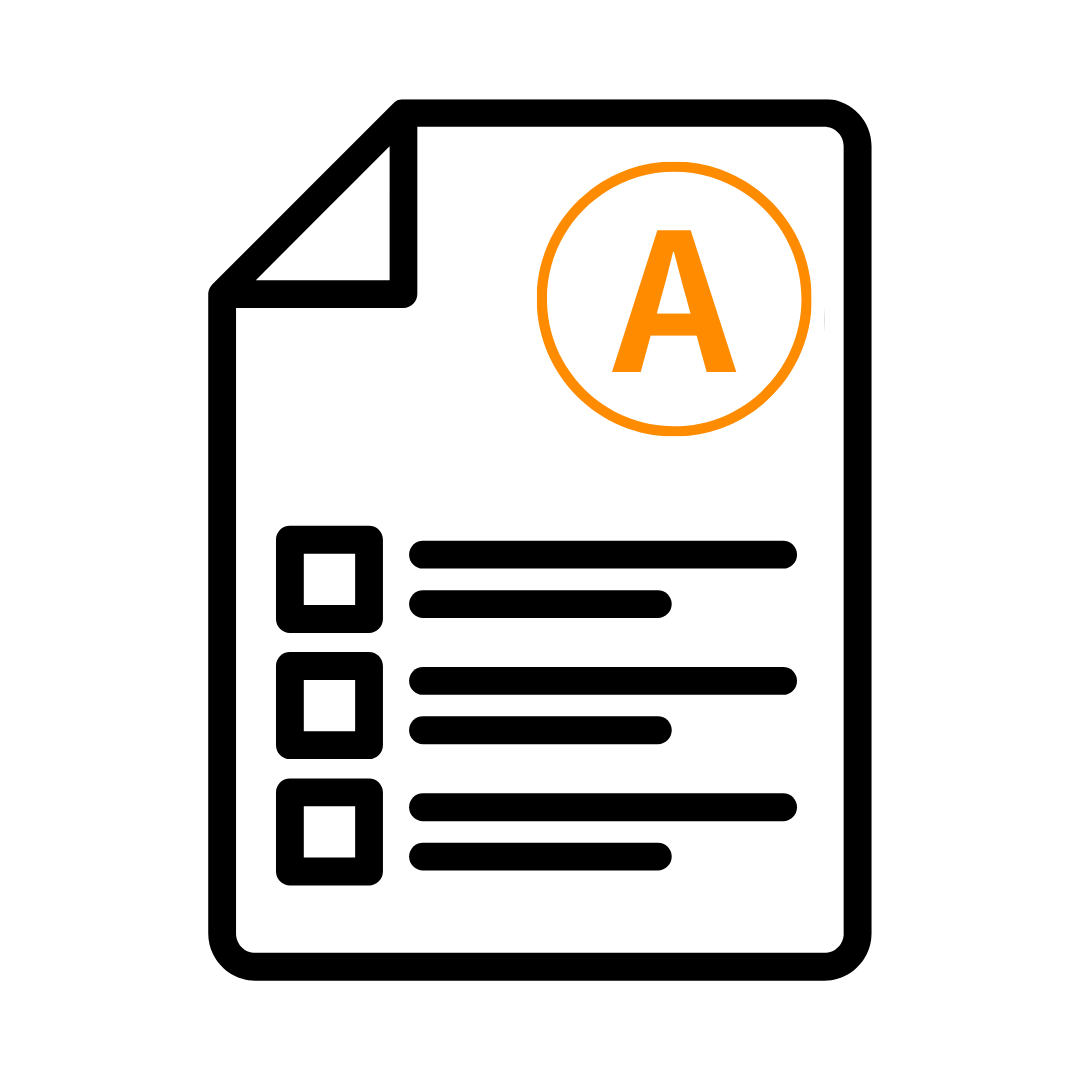
生徒の成績につながる
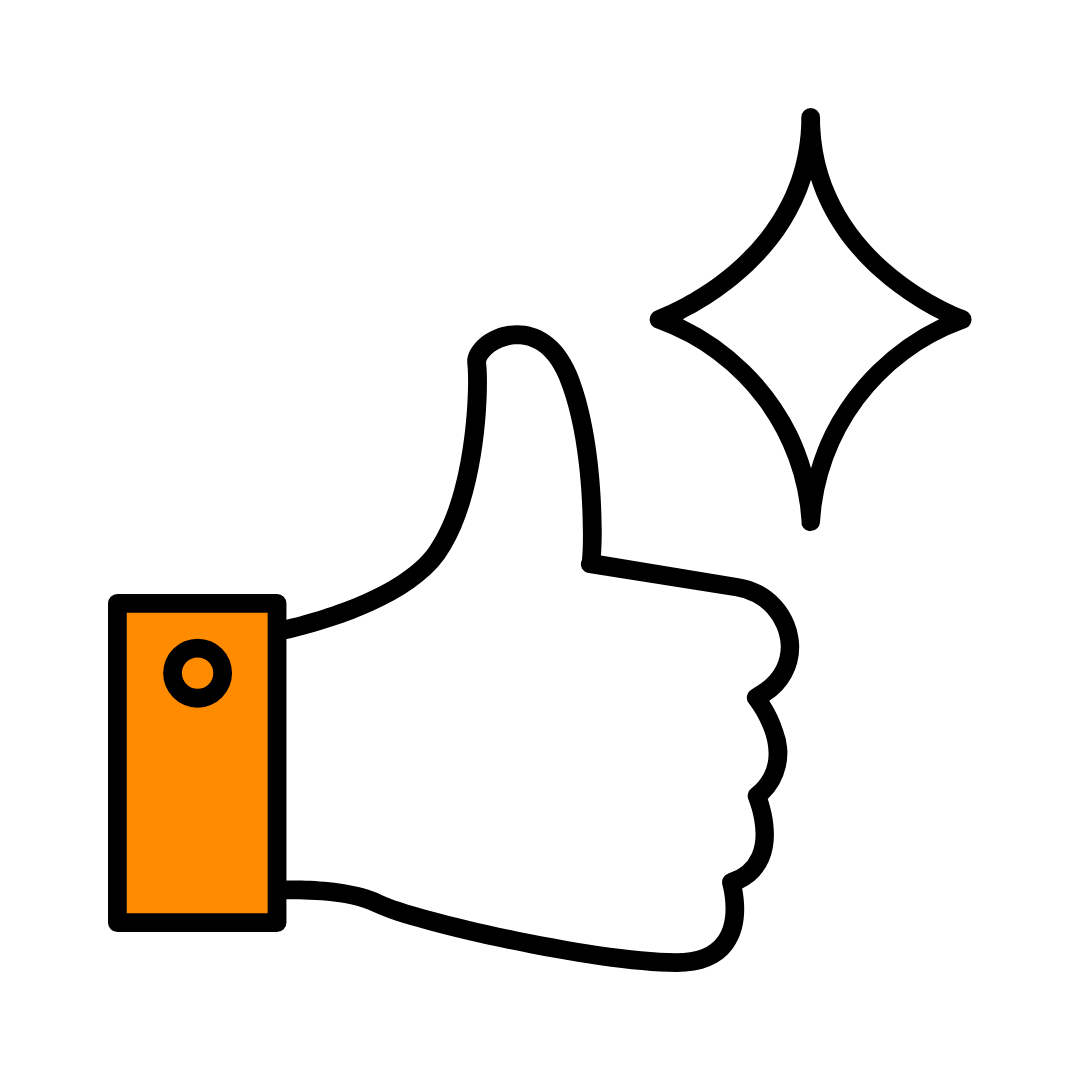
退塾する生徒が減る
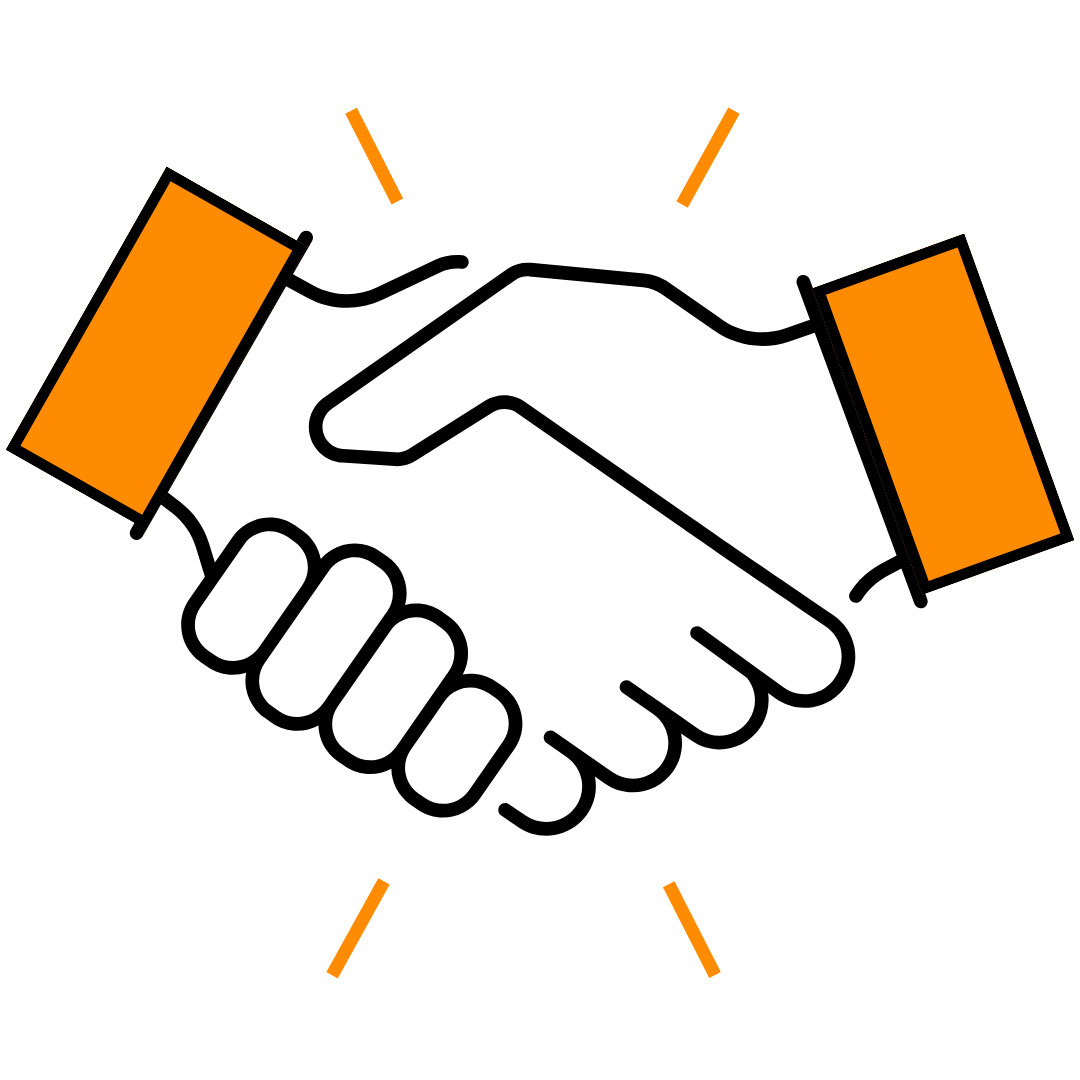
生徒の紹介が増える

講師のやる気が上がる

コミニュケーションに
不安がある講師がいなくなる
いつでもどこでも何人でも見放題で
年間1万円(月々833円)
コーチングスタディ講師紹介

沖津亮佑
大学生の時に東京都世田谷区で小中高生対象の個別指導塾を創業し、自塾でコーチング研修を講師に実施することで、第一志望合格率100%を達成しました。この研修を全国の学習塾さんにも体験してもらいたいと思い、2018年から関東と関西の学習塾さんを中心に、出張コーチング研修を始めました。そして2022年、もっとたくさんの学習塾さんがコーチング指導を手軽に取り入れられるよう、今まで行ってきた研修の内容を動画にしたサービスを始めました。
2013年-東京都世田谷区で小中高対象個別指導塾を開業
2016年-銀座コーチングスクールでコーチング学び始める
2018年-大学受験第一志望合格率100%達成
2018年-外部向けコーチング研修開始
2019年-茨城県水戸市でコーチング指導塾セルフクリエイトを開業
2020年-教育コーチング育成機関Edcoac立ち上げ
2021年-セルフクリエイト2校舎目開校
2022年-コーチングスタディβ版リリース